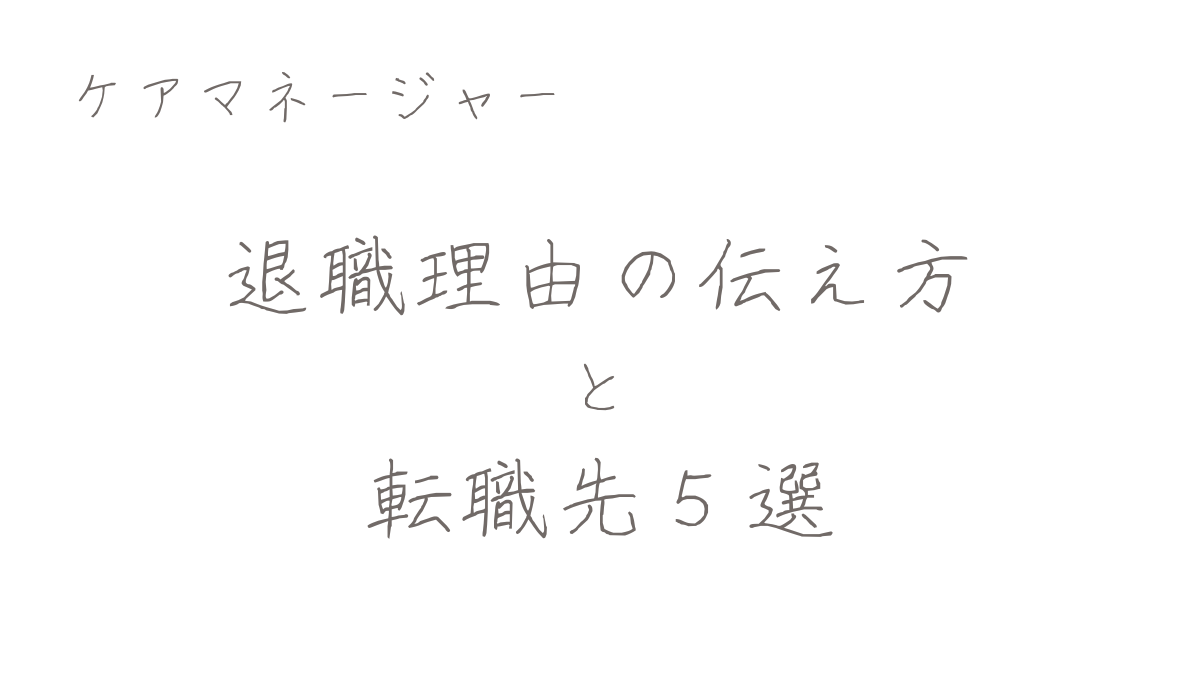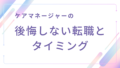ケアマネ辞めたい…みんなの退職を決めた理由
「もう限界かも…」
「このまま定年まで続けるなんて無理…」
ケアマネとして働いていると、ふとそんな気持ちがよぎる瞬間がありますよね。
ここでは、ケアマネを辞めた人が実際に抱えた理由を整理してみます。
▽ 書類業務とプレッシャーに疲れた
ケアマネは制度や記録の正確さが求められ、書類業務も膨大。
「いつも何かに追われてる感じがする」
「記録が間違っていないか漏れがないか気を張っている」
そんなプレッシャーに心がすり減っていく人も少なくありません。
▽ 利用者・家族・他職種との板挟みに疲れた
調整役としての立場が多く、“誰にも本音を言えない立場”に追い込まれがち。
感謝されることもありますが、クレームや無理な要望にさらされることも。
「なんで自分だけこんなに…」と孤独感を抱えてしまう人もいます。
▽ ケアマネとしての将来像が見えない
「定年までこのまま続けられる気がしない」
「ステップアップの道が見えない」「給与が上がらない」
そんな不安から、キャリアの見直しを考える人もいます。
特に30〜40代で「今が転機かも」と感じるケースも多いです。
▽ 職場の体制に限界を感じた
1人ケアマネで休みが取れない。
管理者が仕事量の調整をしてくれない。
常に人手不足で持ち帰り仕事が当たり前。
など、「ケアマネが続けられない理由」=「働く環境に問題がある」場合も。
「ケアマネという職業がイヤなのか?」
「今の職場が合っていないだけか?」を整理することが大切です。
退職の伝え方で気をつけたいポイント
「辞めます」と伝えるのって、想像以上にハードルが高いもの。
特にケアマネは、担当利用者との関係やチーム内の調整もあるため、
“自分が抜けたら迷惑かも…”と遠慮してしまう人も多いですよね。
ここでは、スムーズかつトラブルにならない退職の伝え方のポイントをまとめました。
▽ よく使われる退職理由はこれ
本音をすべて話す必要はありません。
大切なのは「納得されやすく、引き止められにくい理由」を選ぶこと。
・家庭の事情(介護・子育て・配偶者の転勤など)
・体調不良・心身のリズムを整えたい
・キャリアの見直し・今後の働き方を考えたい
→ “仕方がない事情”+“前向きな言い方”がセットだと伝えやすく、相手も理解しやすいです。
▽ 嘘にならない“建前”の作り方
「正直に話したいけど、全部言うのは気が引ける…」という人も多いはず。
たとえば:
✅(本音)もう業務量が限界 →
☑️(建前)家庭との両立が難しくなり、見直すことにしました
✅(本音)人間関係がつらい →
☑️(建前)今後は違う働き方にも目を向けたいと考えるようになりました
→ 嘘にならない程度で、角が立たず、自分を守れる言い方を考えておきましょう。
▽ 引き止めへの対処法も考えておこう
「もう少しだけ頑張ってみない?」
「あなたが辞めたら困るよ」
…そんな言葉に心が揺れるかもしれませんが、辞めたい理由がはっきりしているなら
ブレないことが大事です。
「すでに家族とも話し合って決めました」
「心身の回復を優先したいと考えています」
など、しっかりとした意志を伝えることで、引き止めもやんわり断りやすくなります。
▽ 辞めるタイミングは“配慮+自分の限界”のバランスで
担当利用者の変更・引き継ぎに配慮しつつ、
自分の心身の限界を超える前に動くのが鉄則。
目安としては、退職の1〜2ヶ月前には申し出るのが一般的。
特にケアマネの場合は、次のケアマネが決まってから引き継ぎ期間が
必要になるため、少し早めの行動を心がけましょう。
ケアマネの転職先おすすめ5選
「辞めたいけど、その後どうしよう…」
法人を変えるだけでも、働きやすくなることも多いですし、
ケアマネとしての経験は、実は他の職種でもかなり活かせる武器になります。
ここでは、働きやすさややりがい、スキルの活用度をふまえて、
転職先として人気の職種を5つご紹介します。
① 地域包括支援センターの相談員
介護予防や高齢者支援を中心に、地域全体の福祉向上を担う役割。
ケアマネの知識が活かせるほか、中立的な立場で支援できるのが大きな魅力。
✅ 向いている人:多職種連携が得意、全体調整が好きな人
✅ 働き方:身体介助はほぼなし、土日休みのところもあり
② 医療事務・クリニック受付
レセプトや制度の知識、患者対応スキルが活かせる職種。
体力的負担が少なく、ライフスタイルを重視したい人に人気。
✅ 向いている人:正確な事務作業や接客が得意な人
✅ 働き方:クリニック勤務なら残業少なめ・パート可の求人も多い
③ 福祉用具専門相談員・介護用品関連の営業職
福祉用具の提案やレンタルプラン作成など、ケアプラン経験が強みになる分野。
✅ 向いている人:人と話すのが好き、外出の多い仕事が苦にならない人
✅ 働き方:営業職だが現場経験者の信頼度は高く、未経験からでも採用されやすい
④ 高齢者施設の管理職・運営スタッフ
特養・有料老人ホーム・小規模多機能などで、ケアマネ経験を活かしながら現場のマネジメントに関わるポジション。
✅ 向いている人:リーダーシップがある、全体を俯瞰して調整できる人
✅ 働き方:やや多忙だが、給与・待遇が改善されるケースもあり
⑤ 社会福祉協議会・NPO法人など福祉系事務職
制度理解や調整経験を活かし、地域活動や行政と連携する支援業務に関われる。
✅ 向いている人:現場を離れても福祉に関わりたい人、コツコツ型
✅ 働き方:土日祝休みや残業少なめのケースが多く、長く働きやすい
「ケアマネしかできない」と思い込んでいた人も、
選び方次第で、“これなら自分でも続けられそう”という仕事がきっと見つかります。
施設ケアマネと居宅ケアマネ、次に選ぶならどっち?
「ケアマネを辞めたい」と思ったとき、“仕事そのもの”が合っていないのか、
それとも“働く環境”が合っていないのか、を見極めることが大切です。
上記の5つの就職先とは別に、「施設ケアマネ」と「居宅ケアマネ」だと
どっちが良いんだろうと思う人も多くいます。
ここで、それぞれの違いを明確に比較してみましょう。
| 項目 | 施設ケアマネ | 居宅ケアマネ |
|---|---|---|
| 勤務場所 | 特養、有料、小規模多機能などの施設内 | 居宅介護支援事業所(訪問あり) |
| 担当利用者 | 施設入居者のみ | 地域の在宅高齢者(訪問対応) |
| 書類作成量 | 少なめ〜中程度 | 多め(モニタリングや記録含む) |
| 他職種連携 | 同じ施設内でスムーズ | サービス提供者との調整が必要 |
| 兼務の可能性 | 介護職との兼務があることも | ケアマネ専任が基本 |
| 勤務形態 | シフト制/夜勤対応ありの場合も | 日勤のみ/土日休みも選べる |
| 向いている人 | 現場との一体感を大事にしたい人 | 自分のペースで進めたい人・ 外部と調整が苦でない人 |
✅ 判断ポイントの例
「夜勤やシフト制がしんどい」→ 日勤中心の居宅がおすすめ
「孤独な業務が苦手」→ チーム内で協力しやすい施設が合うかも
「訪問業務より、固定施設内で完結する方が気楽」→ 施設向き
「業務範囲が広すぎて疲れた」→ 施設の方が負担が少ないケースも
「ケアマネを辞める」のではなく、「働く場を変える」選択肢も大切です。
ケアマネに強い転職サイトおすすめ3選
「次はもっと自分に合った職場で働きたい」でも、転職にはやっぱり労力がいるから
なかなか1歩が前に出れない。
そんな人におすすめなのが、介護・福祉業界に特化した転職支援サービス。
ここでは、サポート力・求人の質・使いやすさで選んだ3社をご紹介します。
✅ 1. 介護・福祉の転職サイト『介護JJ』|好条件の非公開求人多数!
介護業界専門の転職サイトで、ケアマネ求人や相談職への転職にも強いのが特徴。
非公開求人が多く、経験に合った職場を丁寧に提案してくれます。
📌 求人例:居宅ケアマネ、施設ケアマネ、生活相談員、管理者候補など
📌 サポート:電話・メール・LINEでの柔軟な対応、履歴書添削や面接対策あり
📌 対応エリア:全国対応
👉 「年収アップや働きやすさを重視したい人」におすすめ!
✅ 2. かいご畑|未経験・ブランクOK!資格取得支援も◎
未経験からの転職支援やキャリアチェンジを応援してくれるサービス。
資格支援制度があり、「現場経験を活かして新しい働き方を探したい人」にぴったり。
📌 求人例:ケアマネ、介護職、相談員、サービス提供責任者など
📌 サポート:無料のキャリア相談/介護資格取得支援制度あり
📌 対応エリア:全国(北海道、関東、関西、北陸、東海、中国、九州地方エリアに強み)
👉 「働きながらキャリアアップしたい」「ブランク明けでも不安なく始めたい」人に◎
✅ 3. 【ジョブソエル】|女性に寄り添う転職サポートが魅力
「家庭と両立したい」「人間関係の良い職場がいい」
そんな女性ケアマネの悩みに寄り添った提案をしてくれる、福祉・医療系特化の転職エージェント。
📌 求人例:居宅ケアマネ、地域包括、医療事務、訪問事業所など
📌 サポート:専任アドバイザーによる女性向けサポート/職場の雰囲気まで伝えてくれる
📌 対応エリア:全国
👉 「今度こそ働きやすい職場に出会いたい」という人におすすめ!
✅ どれか1つに絞れないときは…
まずは2〜3社に登録して、比較しながら相談するのが成功のカギ!
それぞれの強みを活かして、自分に合った転職先をじっくり選びましょう。
スムーズに辞めるために準備しておきたいこと
「辞めたい」と思っても、いざ実際に動くとなると不安や手間がつきもの。
ここでは、トラブルなくスムーズに退職するためにやっておきたい準備をまとめました。
▽ 有休・退職日を早めに確認しておく
ケアマネは引き継ぎに時間がかかることが多いため、退職の意志は早めに伝えるのがマナー。
可能なら、有休の残日数も事前に確認し、“消化前提でスケジュールを組む”のが◎。
▽ 担当利用者の引き継ぎ資料を準備する
退職時にバタバタしないよう、担当利用者の情報は簡易的にまとめておくのがおすすめ。
記録類は日頃から整えておくと、急な申し出にも対応しやすくなります。
▽ 離職票や雇用保険の手続きを確認
次の仕事が決まっていない場合は、失業保険の受給や職業訓練の申請も視野に。
離職票の発行タイミングや手続きについては、事前に事務担当へ相談しておくと安心です。
▽ 転職活動は並行して進めるのが◎
「辞めてから考えよう」と思っていたら、収入が途絶えて焦って決めてしまう…なんてことも。
余裕を持って選ぶためにも、現職中から少しずつ情報収集や登録を進めておくのがベストです。
辞めることは“逃げ”ではなく、“自分を守る選択”。
焦らず、一歩ずつで大丈夫です。